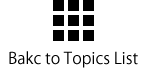「お客様の想いをカタチに」
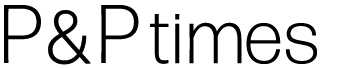
July / August 2025

1
P×Ptalk
ミシュランの星を16年連続※で獲得し続けるオーナーシェフ、
その横顔には大阪の下町で育ったやんちゃ坊主の面影が垣間見える
「P×P talk」は、当社代表廣川信也が各界で活躍するリーダーと、ビジネスや人生について語り合う対談企画です。
今回の対談のゲストは、「Fujiya 1935」のオーナーシェフ 藤原哲也氏です。

「Fujiya 1935」オーナーシェフ
藤原 哲也氏ふじわらてつや
1974年4月1日大阪生まれ。親子四代にわたる生粋の料理人一家に生まれる。専門学校にてフランス料理/製菓を勉強後、ホテル勤務を経て、24歳で渡伊。イタリアで修行後、勉強の為に訪れたスペインにて、先進的な現代スペイン料理の流れに感銘を受け、スペインへ。シェフが現役の脳神経外医としても知られる「L’ESGUARD(レスグアルド)」にて経験を重ねる。
2003年に帰国後は、先代からのお店を引き継ぎ「Fujiya 1935」をスタートさせる。
01
藤原 料理の技術はほぼ継承していません。祖父までは汁物屋、父親は洋食屋、だから料理自体もその技術も継承していません。ただ商売というかお客様に対する心得はずっと継承しています。小さいころからずっと背中を見せられてきました。一番印象に残っている言葉は「お客さんの後ろにお客さんがいる」という祖母の言葉です。
廣川 なるほど!つまり実際見えているお客様の後ろには見えてはいないけど無数のお客様がいる。だから目の前にいる一人一人のお客様を大切にしないといけないと。船場・大阪の商人の魂、心意気がたまたま料理の世界で受け継がれてきた。マインドの上に「料理」が載って続いている。そんな感じですね。
藤原 また祖父は一言でいうと「ハイカラな人」で、英語を覚えたり海外渡航をしたりしていました。父も本当はフランスに行きたくてフランス語の勉強までしていたのですが、お見合結婚して行けなくなり、代わりにその夢を託されたのが僕という訳です。長男なので「後を継ぎなさい!」とずっといわばマインドコントロールされ続けていましたが、敷かれたレールの上を走るだけでは面白くないので、自分も外へ出ようとイタリアへ。そして新しい風が吹き始めていたスペインへと向かいました。

父は悩んだ末に「哲也の言う通りにする」と言ってくれて、洋食をやめ脇役に徹し、魚をさばいたり、パンを焼く仕事を手伝ってもらいました。ですが、お互い藤原家の血を継いでいるので気が強く、取っ組み合いになるくらいの喧嘩が絶えませんでした。最初は閑古鳥が鳴いていて、それが喧嘩する理由でもあったのですが、徐々にお客様も増えてきて「もうそろそろ俺が離れても大丈夫やろう」と父が店を離れて近くで別に洋食屋を再開させました。その父は2000年に他界し、現在は妹夫婦が店を切り盛りしています。
廣川 つまり「革新」は特別に意識して生まれたものではなく、藤原家に宿るDNAそのものであるということですね。
02
目の前にあるものを最大限に活かすために取り入れる
藤原 「21世紀の料理人」として知られるフェラン・アドリア氏がオーナーの、スペインの伝説的レストラン「エル・ブジ」にはずっと興味がありました。イタリアで2年働いた後、知人の予約でようやく訪れることができました。せっかくなので他のクリエイティブな店も紹介を受け、行ってすぐに働くことを決心したのが「レスグアルド」。イタリア語しか話せない僕を快く受け入れてくれました。ここのオーナーシェフのミゲル・サンチェス・ロメラ氏は脳神経外科医でもあり、鍋を置く音しか聞こえないような静寂に包まれたキッチンでした。また色の組み合わせが脳に刺激を与えるとして料理は色彩豊かで、五感で味わうものとして教えられ「五感の料理」と呼ばれていました。これに加えて日本ならではの「季節の移ろい」を国内の豊かな食材で表現することで、幼少期の思い出や原風景を呼び起こしてもらおうという考えに基づいた当店のコンセプトが「季節と記憶の食卓」です。

藤原 当店の料理は優しい味わいが特長で、家族だけでやっている店なので、この「アットホーム感」を示す言葉が「食卓」なのです。
03
人を幸せにする
藤原 あの廊下は13年前の改装時(今回のリニューアルで短縮される予定)のものですが、コンセプト的には移動するたびにシーンが変わっていく、当店の世界観に引き込まれていくという「没入感」の一つです。
廣川 えっ、短くなるのですか!あれは残して欲しかった(笑)。ちなみに廊下を通るのに5.7秒かかりました。
藤原 ウェイティングルームで決まって18時30分にお客様にご挨拶させていただくのですが、コンセプトをお伝えするのにはワクワク感もありますが、同時に「ちゃんとしゃべれるかなぁ?」と思って何年経ってもドキドキしています(笑)。

松屋町筋に面したドアから続く廊下※但し改装後変更

間接照明に包まれたウェイティングルーム
04
製造業における、いわば「用途開発」
藤原 頭の中に残っている、いつかどこかで触れたフレーズが蘇るのです。例えば今回の場合は「雪は音を吸収する」という部分。ああそうなんだぁ...と。それを落とし込むことでポエムが生まれます。また今回の場合、そこからつくしが連想され、ウェイティングルームでお出しする、つくしのお茶が生まれました。お茶の中につくしの頭(芽)が入っています。

藤原 秋から冬にかけて、水辺近くで落ち葉や枯草をかき分けると、その下に頭(芽)の部分だけを地表に出し、春の準備を始めているつくしを見つけることができます。その後暖かくなると茎がでてきます。年が明けると「新春」と言いますが、植物は秋のうちから春の準備をしています。苦みとほんのり甘みがあるつくしの芽をスプーンですくって召し上がっていただくことで静かに近づく春を感じ取っていただければという思いを込めています。
藤原 1月の半ばくらいから漁が始まるシラウオを使って何か料理ができたらと思い、レンコンと合わせてフリットにしました。梅は岡山県の美作の農家さんが切ってきてくれました。

「シラウオとレンコン」

「マグロのチュロス」
藤原 (取材時の2月下旬に)漁場からあがってくるマグロを使って料理したい。特にトロと中トロの部分は油を持っているので人肌くらいで口の中で溶けてちょうどいい塩梅のトロッとした感じになるのでは、と思っていたところ、ジャガイモを少し練り込んだチュロスがいいのでは?ということになりました。
藤原 はい、これにはスペインのテクニックが用いられています。一時期、僕自身が飽きてメニューから外したことがあったのですが、お客様がわざわざこれを食べに来ていただいているということで今でも続けています。

「気泡をたくさん含ませた黒豆のパン」

「白甘鯛 ベルガモット」
藤原 年末くらいから市場に出始めるセリを使ってパセリのような感覚で料理をつくれたらと。そこでボンゴレみたいにニンニクでオイルベースのソースをつくってそこに上品な香りのセリとベルガモットを入れて冬場がとても美味しい白甘鯛に合わせて低温で蒸してみました。
藤原 基本的にはその通りです。今(取材時)は食材もちょっとずつ春を感じるものが出て来ているのでそれらをメニューに落とし込んでいます。
廣川 このことは我々製造業にも当てはまります。いくら優れた素材を開発しても用途が見つからず結局日の目を見ずに終わる例を沢山目にしてきていますが、産業界にも、藤原さんのように優れた目利きのできるシェフのような方がいれば、それらの特長が必ず活かせる場所が見つかるということですよね。大いに参考になります。
05
藤原 アリス・ウォータースさんのところには5年くらい前に「確認」しに行きました。
廣川 「確認」とは?
藤原 アメリカとヨーロッパとでは食の環境は全然違っていて「ノーマ」や「エル・ブジ」では出せないあのナチュラルな感覚をどうやって日本の中で取り入れてやっていくのがいいのか考えてレストランを運営していました。そして実際カリフォルニア・バークレーに足を運んで「確認」した結果、答えが違っていることに気がつきました。考えている以上にもっと自然でした。それに影響されてもっとナチュラルに行こうと決めました。最も今はそれを出しすぎたと思って少し戻しにかかっていますが(笑)。
廣川 次の新たなヒント求めに行くとしたら?
藤原 スペインがまた面白くなってきました。次はアンダルシアに向かいます。そこに2つのミシュラン3つ星レストランがあって、誰も食べたことのないようなマグロのしっぽとか、誰も見たことのないような近くでとれた海藻など、海という「食料庫」の持続可能性を追求し、海産物だけで食事を提供することを目指しています。それをみて刺激を受けたいと思っています。美味しいものを食べるというのも重要ですが、体験や感動がもっと大切です。ナチュラルな方向に寄りすぎていたので、もう少し楽しい感覚、体験する感覚を呼び戻したいと思っています。
廣川 藤原さんのお店は確かに「イノベーティブ」とジャンル分けされるくらい「独創的」ではありますが、決して「独善的」にならないように他のレストランに出向き、定期的に「答え合わせ」をしているのですね。
06

藤原 お客様の満足度は、お店の外にお客様が出られて帰路につく時に顔に表れます。満足いただけているかどうかはその時の笑顔でわかります。それからキッチンにいても、返ってきたお皿の状態ですぐにわかります。
廣川 それは営業活動と同じですね。受注報告は嬉々としてすぐに行われますが、失注はすぐには報告されません。顧客満足度は「笑顔」だけではなく、残した「皿の上」もしっかり見ないと向上しないということですね。
07
藤原 そう思います。コンセプトが「季節と記憶の食卓」なので、幼いころの「記憶」が普通に料理に組み込まれています。大阪のこの地だったからできた料理も多いのです。例えば父親がだんじりが始まる前の8月末に土佐酢をつけて食べるワタリガニを宴会の和食として提供したり、夏祭りにはお頭つきのエビフライを食べさせてもらった幼い頃の記憶です。料理は継承していないとは言いましたが、小学校の頃から皿洗い、盛り付けを、高校生の頃には魚や肉の筋引きなどをやらされていました。子供は暇やったら家を手伝うのが当たり前の時代でした。切っても切り離せない自分の記憶が料理の一部になっていて、そこに「大阪」がしみ込んでいるのだと思います。他の地でやっていたら「イノベーティブ」ではなく、もっとスペイン的なものになっていたかもしれません。「イノベーティブ」=「独創的」であるためには自分を掘り下げ、自分の記憶を探っていかなければならず、これは自分が生まれ育った大阪だからこそできた作業だと思っています。ちなみに「イノベーティブ」はミシュランが設定したジャンルです。今はジャンルそのものが時代遅れだと思っていて、本当はジャンルなんて書いてほしくないくらいなのですが…。
08
藤原 中東さんは家族からは教わらなかった「山の人の感覚」です。「京都の人、山の人が人に対して優しくするとはこういうことなんや!」ということを言葉も含めて教えてもらいました。どういう風に野菜を使うか、といった日本人の心の部分かなぁと。また佐々木さんには「男前の感覚、男っぽい心意気」とでも言えばいいのか、とにかく僕には全然ない感覚で、それを学びたくて足繁く通いました。
廣川 自分の価値観に合うとか自分のやってきたことに合致するから尊敬することもありますが、藤原さんの場合は自分にないものを埋めていく、そういうところに尊敬の念が生まれるのですね。
藤原 そうですね、憧れて好きになる。「こういう人になりたい」と。でも完全にコピーはしません。逆に行き過ぎていると感じたらパッと我に返ることができる、そういう距離感は大切にしています。

09
藤原 逆に縮小の方向に向かわせています。今回の改装で18人くらい入るレイアウトを8〜9名に縮小します。自分もスタッフも料理に集中できる環境をつくることが自分の使命だと思っているからです。それが顧客の支持を維持することにつながると思っています。
 1950年代のふじ家(左)祖母のウメノと(右)祖父の正美 / 1970年代のふじ家。その後、息子達が手伝う洋食店に。
1950年代のふじ家(左)祖母のウメノと(右)祖父の正美 / 1970年代のふじ家。その後、息子達が手伝う洋食店に。10
藤原 行ったら変わると思います。初めに行くきっかけがあったら変わると思います。
廣川 藤原さんの場合、それはどんなきっかけですか?
藤原 父親が僕にフランス料理をさせたかったので「行け行け」と言ってくれました。これがきっかけです。
廣川 それだけフランス料理をやれやれ、と言われたのに従わなかったのですか?
藤原 はじめはホテルでフランス料理をやっていましたが、やはり自我が芽生え、やっぱり違うかなぁと。パスタを上手につくりたい、という気持ちが強くなって結局はイタリアを選んだのですけどね、海外に行くことは絶対いいと思います。生活したら変わるし、移動したら移動した分だけ感覚が変わります。もうとにかく遠いところに行った方がいいとお店の若い子にも言うのです。
廣川 ほとんどの場合、きっかけは待っていてもやって来ないので、自分で作るしかないでしょうし、藤原さんのようにたとえ周囲がきっかけを作ってくれてもそれを活かさなければ何も変わらないということですね。また海外で経験したことがこうやって生まれ育った地に戻って、そこにあるものと掛け合わされて新しい独創的な価値を生み出すという、大きな可能性を秘めたお話を今日は聞くことができました。本当にありがとうございました。
メールマガジン配信開始のお知らせ
廣川ではアイデアのヒントになる「モノづくり」の発想や企画をご紹介し、多くの方が「こんなものが欲しかった!」と思える商品づくりを応援しています。ぜひメールマガジンをご活用ください。

2
現場からのセレクト情報
「飯ごう」をモチーフにしたプラスチック容器の新商品をご紹介!

「鎬(しのぎ)」にフォーカスした商品の価値を最大限に伝えるパッケージ
 ※鎬(しのぎ)とは、刀を横から見たときに中央に入っているラインのことを指します。包丁の用語としては、研磨をしたところと、していないところの境目を指します。
※鎬(しのぎ)とは、刀を横から見たときに中央に入っているラインのことを指します。包丁の用語としては、研磨をしたところと、していないところの境目を指します。美術館を代表するアートをグッズ化!
鳥取県立美術館《ブリロ・ボックス》キャンディ缶

《ブリロ・ボックス》キャンディ缶
サイズ:W65×D65×H70mm
3
前年比1/3削減を実現!
品質・生産性の向上を目指す取り組みをご紹介。

※「2度抜き裁断」とは、食品用プラスチック容器を製造する際に、抜き打ち後、正常に集積されず再度同じ箇所を抜き打ちする抜きトラブルを指します。
 最優秀賞を受賞した「No Plastic Piece」
最優秀賞を受賞した「No Plastic Piece」4
忙しい米国の若い世代は、1日3食の伝統的食慣行から離れ、手軽で健康的な5~6食のミニ・ミールに移行している。大食いで肥満気味のアメリカ人のイメージはもう過去のものだ。長い間米飯はアメリカではメインディッシュの付け合わせ的な存在だったが、今やミニ・ミールの主役の座に躍り出た。ゼネラル・ミルズも、米国で人口が増えているヒスパニック系の消費者向けに、メキシカン風味やチーズピザの香りのスープで味付けしたカップ麺を発売した。米大手スーパーのTargetやコンビニ最大手の7Elevenで本格販売されている。日本人の国民食とも言えるラーメンが米国の地域限定カップ麺のイノベーションとして、圧倒的シェアを誇る日清食品に挑戦するという。米大手食品メーカーの一手が起死回生の妙手となるか、その結果が楽しみだ。
▼参考資料
・ユニリーバのwebsiteはこちら
・General Millsのwebsiteはこちら


5
パケトラ | pake-tra.com
Potbelly(ポットベリー)
記事の続きは「パケトラ」でチェックしてみてください。
(外部リンク)アメリカの代表的なサンドイッチのレストランチェーンとその特徴

6
受け継がれてきたものを大切にする、
切り絵の技術が使われたパッケージ『こ、ふぃなんしぇ』

〒349-1102
埼玉県久喜市栗橋中央一丁目17-1
電話番号:0480-52-5001
営業時間:10:00~16:00
定休日:水曜日・日曜日・祝日
https://tsumugiya.net/ec/(外部リンク)
7
何度でも貼りなおせる吸着シートで空間を気軽に装飾!
商品の用途例
(1)イベント会場や展示会
期間限定のカフェなどの装飾に使用することで、テーマやデザイン変更に合わせて簡単に貼り替えが可能です。季節に合わせて店舗の内装やグラスや小物への装飾として用いることで空間全体の雰囲気を彩ることができます。イベントなどでオリジナリティを演出。必要な数だけご入用いただけます。
(2)ヘルメットや車のボディ
柔らかい素材なので曲面が多い箇所にも難なく貼り付けることができます。雨天時も剥がれることはなく車の塗装が傷つくこともありません。
(3)スマートフォンの裏面
キャラクターなどのステッカーとしてお使いいただけます。飽きたら簡単に剥がすことができます。ケースの内側から貼り付けることもできるためステッカーが汚れる心配もゼロ。

「ミロクなシート®」は主に合成樹脂材料の一つである軟質の塩化ビニールを使用しており薄く柔らかい素材なので折れたり丸めたりしてもシワになりません。素材の色は透明なものと白色のものの2種類あり、数に応じてUV印刷またはオフセット印刷を用いてグラフィックデザインを表現します。頻繁に貼り替えを伴う作業や、見栄えを重視しつつ手軽さを求める場面で利便性を発揮します。イベント企業様、飲食店様、空間デザイン関連企業様をはじめ、幅広い業界で役立つ素材です。グラフィックデザインの作成から承りますのでお気軽にご相談ください。(お問合せは当社パッケージ事業部まで)
8
酸味、香味、辛味が絶妙なバランスの本格中華


住所:〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-6-23 B/2ビル1F
TEL:022-721-6030
アクセス:仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」から徒歩約5分
駐車場:なし※周辺コインパーキング多数あり
営業時間:月~日、祝日、祝日前日
11:30~14:30/17:30~23:00
9
プレゼント!

アメリカで人気のスーパーマーケット「Trader Joes(トレーダージョーズ)」からナチュラルペーパーのエコバッグを3名様にプレゼントします。このエコバッグは、紙製ですが布のような質感で触り心地が良いバッグです。軽量で非常に高い耐久性があり大容量の荷物を入れる事ができます。水にも強く、洗濯(手洗い)が出来るのでアウトドアアクティビティーにも使うことができて便利です。
このキャンペーンは終了しました。
多数のご応募ありがとうございました!